こんにちは、カジです。
皆さんと一緒に「なるほど!」を見つける旅を、また始められることを大変うれしく思っています。この探求の旅に、お付き合いいただければ幸いです。
さて、今回から解剖していく、新たな研究対象。それは、アメリカ・シアトル発のコーヒーチェーン、「スターバックス」です。
まず、その規模を客観的な数値で見てみましょう。2024年度時点で、スターバックスは全世界で約40,199店舗を展開し、年間売上高は362億ドルに達します。これはコーヒーを主軸とするチェーンとしては他に類を見ない規模であり、まさに「世界最大のコーヒーチェーン」という称号にふさわしい存在です。
街を歩けば、緑のサイレンロゴが私たちを迎えてくれます。友人とのおしゃべりに、あるいは一人で集中したい時の作業場所として、多くの人が日常的に利用しているのではないでしょうか。しかし、ふと考えてみると不思議です。コンビニに行けば100円台で淹れたてのコーヒーが買えるこの時代に、なぜ私たちは一杯500円近くするスターバックスのコーヒーを、わざわざ選ぶのでしょうか。
その答えは、コーヒーの味「だけ」にないことは、多くの人が感覚的に理解しているはずです。そこには、私たちを惹きつけてやまない、極めて巧みな「仕組み」が存在します。
今回はその強さの根源である、スターバックスを唯一無二の存在たらしめている「サードプレイス」という概念と、それを具現化する空間設計の秘密に、じっくりと迫ってみたいと思います。
すべては「イタリアの原体験」から始まった
驚くかもしれませんが、スターバックスは元々、ただの「コーヒー豆の焙煎・販売店」でした。今のようなカフェ形態ではなかったのです。その運命を劇的に変えたのが、後にCEOとなり、スターバックスを世界企業へと育て上げたハワード・シュルツ氏です。
1982年、シュルツ氏はスターバックスの小売事業・マーケティング担当責任者として入社します。そして翌年の1983年、彼が国際的な見本市に参加するためイタリアのミラノへ出張したことが、すべての始まりでした。
シュルツ氏は、街の至る所にある「バール(Bar)」の光景に衝撃を受けます。そこは、人々がエスプレッソを片手に会話を楽しみ、バリスタと常連客が親しげに挨拶を交わす、活気に満ちた「コミュニティの拠点」でした。人々はコーヒーを飲むためだけにそこにいるのではなく、豊かな人間関係と時間を過ごすために集まっていたのです。
この体験を通じて、シュルツ氏は天啓を得ます。スターバックスが本当に売るべきものは、コーヒー豆という「モノ」ではなく、人々が集い、くつろぎ、人間的なつながりを感じられる「体験」であると確信したのです。
しかし、シアトルに戻った彼の熱意は、創業者たちに受け入れられませんでした。彼らはあくまで高品質なコーヒー豆を売ることにこだわり、「レストランビジネス」に参入する気はなかったのです。自らのビジョンを実現するため、シュルツ氏は1985年にスターバックスを退社し、自身のコーヒーバーチェーン「イル・ジョルナーレ」を設立します。
そして運命の転機が訪れたのが1987年8月。スターバックスの創業者たちが事業の売却を決定し、シュルツ氏は投資家から資金を調達して、古巣であるスターバックスを買収。自らのビジョンを、スターバックスというブランドで実現していくことになったのです。
「サードプレイス」という、強力な設計図
シュルツ氏がイタリアで直感的に捉えたビジョンは、偶然にも、ある社会学者の理論と完璧に共鳴するものでした。その理論こそが「サードプレイス(Third Place)」です。
この言葉は、アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグが、1989年に発行された著書『The Great Good Place』の中で提唱した概念です。
オルデンバーグ氏によれば、人々には心安らぐ場所が三つ必要だといいます。
- 第一の場所(ファーストプレイス): 自宅
- 第二の場所(セカンドプレイス): 職場や学校
- 第三の場所(サードプレイス): そのどちらでもない、心が安らぎ、リラックスして過ごせる「とびきり居心地の良い場所」
彼は、当時のアメリカ社会が自宅と職場の往復だけの生活に陥りがちで、人々が気軽に集える非公式な公共の場が失われていると警鐘を鳴らしました。そして、この失われたコミュニティの「錨(いかり)」として、誰もが平等に受け入れられ、会話が主役となるような場所の重要性を説いたのです。
スターバックスの経営陣は、この理論を自社のビジネス戦略に不可欠な要素として取り込みました。彼らは自らを単なるコーヒー販売業者ではなく、現代社会が抱える「孤独」や「断絶」という課題に対する一つの解決策として位置づけることに成功したのです。この高尚な社会的使命が、プレミアムな価格設定を正当化し、他の安価なコーヒーチェーンとの明確な差別化を可能にしました。
「居心地の良さ」を構成する、緻密な空間設計

では、スターバックスはどのようにして、この「サードプレイス」という抽象的な概念を、具体的な「居心地の良さ」として店舗に落とし込んでいるのでしょうか。その空間には、私たちの五感に働きかける、緻密に計算された仕組みが隠されています。
- 光と色の心理学
スターバックスは、一般的な小売店に見られるような均一で明るい照明を意図的に避けます。代わりに採用されているのは、スポットライトなどでテーブルの上だけを照らし、天井などの他のエリアは暗めに保つという「光と影の劇的な演出」です。これにより、空間に親密な雰囲気が生まれ、私たちの視線は自らのパーソナルスペースへと自然に導かれます。 - キュレーションされた音響空間
店内で流れるBGMは、各店舗の裁量ではなく、本社で一元的に管理・選曲されています。そのプレイリストは、単一のジャンルに偏ることなく、時間帯に合わせて変化するように設計されています。誰もが知る曲のジャズアレンジなど、「聴き覚えのある音楽」と「初めて聴く音楽」を巧みに組み合わせることで、心地よくも退屈させない音響空間を創り出しているのです。 - 素材と座席の振り付け
店内を見渡すと、テーブルやカウンターなど、多くの場所に「木」が使われていることに気づきます。これは、木が持つ自然な温かみが、リラックスした「わが家」のような感覚を生み出すのに貢献しているからです。座席も、一人で集中したい人のための小さな丸テーブルから、グループで会話を楽しむための大きなコミュニティテーブルや柔らかいアームチェアまで、多様なニーズに応えるように配置されています。
究極の価値は「人」と「体験」
しかし、どれだけ空間を作り込んでも、それだけでは無機質な箱に過ぎません。スターバックスが提供する価値の中核は、そこで働く「人」が生み出す、ポジティブな「体験」にあります。
スターバックスでは、すべての従業員を「パートナー」と呼びます。これは、1991年に導入された「ビーンストック」という自社株購入権プログラムに由来し、会社の成功を全員で分かち合う仲間であるという考えを象徴しています。
彼らには、台本通りの接客マニュアルではなく、「グリーンエプロンブック」という小さな手帳が渡されます。そこには、「歓迎する」「心を込めて」といった5つの基本原則が記されており、業務の「方法」ではなく、その仕事の「理由」が示されています。この哲学的な指針が、パートナー一人ひとりの主体性を促し、顧客との真のつながりを生み出すのです。
カップに名前やメッセージを書いてくれる、あのささやかな行為も、元々は複雑化する注文を管理するための業務上の必要性から始まり、やがてパートナーたちが自然発生的に進化させたコミュニケーションの形だといいます。
まとめ
スターバックスの本当の商品は、コーヒー豆という「モノ」ではなく、「スターバックスで過ごす豊かな時間」という「体験」そのものです。
ハワード・シュルツ氏がイタリアで発見した「コミュニティの拠点」という原体験を、「サードプレイス」という強力な設計図へと昇華させ、それを店舗デザイン、音楽、そして「パートナー」による接客といった、あらゆる要素に一貫して落とし込む。この見事な「仕組み」こそが、スターバックスを単なるコーヒーショップではない、特別な存在へと押し上げたのです。
彼らは、現代人が心のどこかで求めている「居場所が欲しい」という根源的な欲求を見抜き、その完璧な「解」を、一杯のコーヒーと共に差し出してくれた。私は、そう考えています。
【挿絵について】
本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。
さて、今回は空間という「ハードウェア」の秘密に迫りました。次回は、多くの人を惹きつけてやまない「フラペチーノ®」を題材に、スターバックスの巧みなマーケティングという「ソフトウェア」の仕組みを解剖してみたいと思います。
それでは、また次の探求でお会いしましょう。


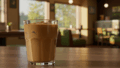
コメント