こんにちは、カジです。
前回は、商業的に苦戦したゲームキューブから、いかにして数々の名作IPが生まれたかを見てきました。では、なぜマリオ、ゼルダ、ポケモンといった任天堂のキャラクターたちは、これほどまでに強く、長く、世界中の人々に愛され続けるのでしょうか。
その人気は、我々の想像を遥かに超える規模に達しています。例えば、『ポケモン』は全世界での累計総収益が13兆円を超え、ミッキーマウスやスター・ウォーズをも上回る、歴史上最も成功したメディアフランチャイズです。2023年の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』は、全世界で2000億円以上の興行収入を記録する歴史的な大ヒットとなりました。
これは決して偶然ではありません。そこには、キャラクターという「資産」の価値を最大化するための、任天堂ならではの、極めて合理的で、徹底された「メカニズム」が存在します。今回は、その秘密を「3つの鉄則」として解き明かしてみましょう。
鉄則①:キャラクターを“機能”から切り離さない
多くのキャラクターは、物語や見た目(デザイン)から作られます。しかし、任天堂のキャラクター、特にマリオは「ジャンプする」という機能(遊び)から生まれました。
彼の存在理由は、物語を語ることではなく、プレイヤーが操作して「気持ちいい」と感じるための、最高の「インターフェース」であることです。有名な話ですが、彼に帽子があるのは、ドット絵で髪の毛のアニメーションを描くのが困難だったため。そして口ひげは、口を描かずとも顔の向きを分かりやすくするための、いずれも厳しい制約から生まれた「機能的」なデザインでした。
この「機能との一体化」という思想は、他のキャラクターにも貫かれています。リンクが剣を振る、カービィが吸い込む。任天堂のキャラクターは、常に「どんな遊びをさせるか」という動詞と固く結びついています。だからこそ、彼らの魅力は言語や文化の壁を越え、コントローラーを握った瞬間に、世界中の誰もがその楽しさを直感的に理解できるのです。
鉄則②:徹底した“世界観”の管理
任天堂のキャラクターは、決して何でも屋ではありません。彼らは、任天堂という名の「劇団」に所属する俳優のようなものです。そして、その劇団は、俳優のブランド価値が損なわれるような仕事、例えばキャラクターのイメージを壊すような提携には、極めて慎重な姿勢で臨みます。
その象徴が、映像化戦略の歴史です。1993年の実写映画『スーパーマリオ』の失敗は、IPの創造的なコントロールを他社に委ねることの危険性を、任天堂に痛感させました。その教訓から、2023年の『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』では、マリオの生みの親である宮本茂氏自身が共同プロデューサーとして制作に深く関与し、原作への深い敬意に満ちた作品を大成功に導きました。
この徹底した「世界観のコントロール」は、海外展開にも見て取れます。例えば、『星のカービィ』のゲームパッケージは、日本では可愛らしい笑顔ですが、北米版では眉をつり上げた勇ましい表情に変更されていました。これは、当時の米国の子供たちに「タフで力強いキャラクター」としてアピールするための、計算された戦略でした。
この鉄壁の管理こそが、ブランド価値の毀損を防ぎ、キャラクターの寿命を延ばしているのです。
鉄則③:新しい“舞台”を与え、進化させ続ける
愛されるキャラクターは、ただ古いままではいられません。任天堂の最大の強みは、新しい「舞台(ハードウェア)」を自ら創造できることです。そして、その新しい舞台が登場するたびに、マリオに「新しい役割(新しい遊び)」を与え、常にファンを驚かせ、進化させてきました。
ファミコンでは2D空間を右に進むだけだったマリオは、NINTENDO64では3Dスティックと共に3次元空間を自由に走り回るようになり、WiiではWiiリモコンを振って宇宙を飛び回りました。そしてNintendo Switchでは、帽子を投げて敵やモノに乗り移る「キャプチャー」能力まで手に入れました。
ハードの進化と共に、キャラクター自身がその体験価値を更新し続ける。この「継続的な再発明」のサイクルこそが、40年以上経ってもファンを飽きさせない、究極のメカニズムなのです。
まとめ
つまり、任天堂のIP戦略のメカニズムとは、
「①機能と一体化した強力なキャラクターを生み出し」
「②徹底した世界観管理でブランド価値を守り」
「③新しいハードと共に絶えず再発明し続ける」
という、完璧なエコシステムなのです。
マリオがミッキーマウスのような文化的アイコンになれたのは、この鉄壁のメカニズムがあったからに他なりません。
【挿絵について】
本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。
今回は、任天堂の強さの源泉であるIP戦略に迫りました。では次回は、この強力な哲学とIPを率いた、伝説的な経営者、『岩田聡氏の経営哲学』を解剖してみたいと思います。
それでは、また次の探求でお会いしましょう。
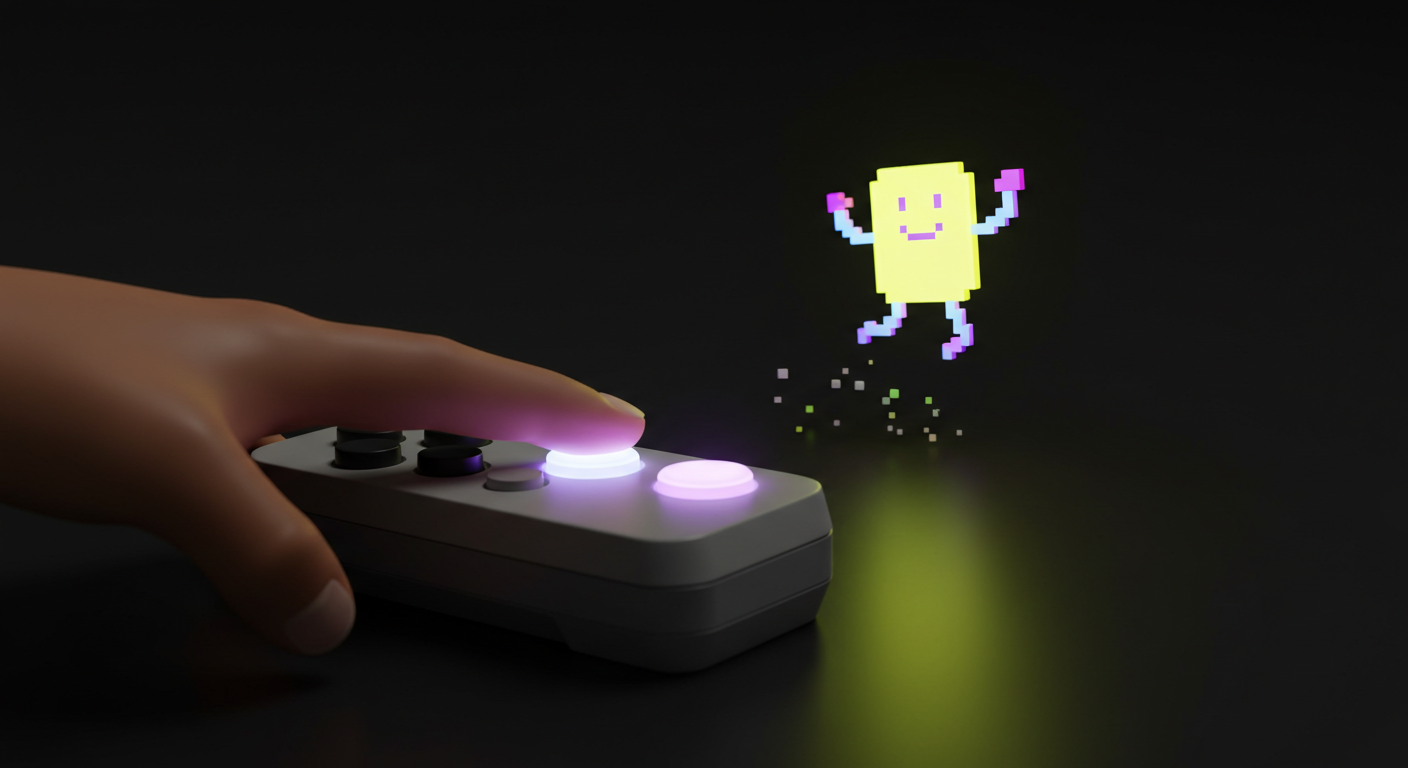
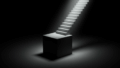
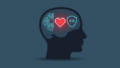
コメント