こんにちは、カジです。
これまでの4回にわたる探求で、私たちはスターバックスという巨大なシステムを、「空間」「商品」「人」「デジタル」という様々な角度から解剖してきました。その成功の裏側には、常に緻密に計算された、見事な「仕組み」が存在していましたね。
しかし、その成功自体が、今のスターバックスに、ある大きな問いを投げかけています。
ブランドの原点である、あの心地よい「居場所(サードプレイス)」という価値。それが、多くの人が利用するモバイルオーダー&ペイがもたらした、圧倒的な「利便性」によって、揺らぎ始めているのです。
今回はこのシリーズの締めくくりとして、この大きな課題にスターバックスがどう立ち向かおうとしているのか、その未来の設計図を解き明かしてみたいと思います。
成功が生んだジレンマ:「コミュニティ」 vs 「利便性」
ITエンジニアである私の目から見ると、現在のスターバックスが直面している問題は、古いシステムに新しい機能を後付けした時に起こる、典型的なトラブルに似ています。
長年、安定して稼働してきた「サードプレイス」という名の基幹システム。そこに、「モバイルオーダー&ペイ」という、誰もが待ち望んだ便利な新機能を接続したところ、予想をはるかに超えるアクセスが殺到してしまいました。
その結果、レジの行列は解消されたものの、今度は商品を受け取るカウンターという別の場所にアクセスが集中し、システム全体が混雑する「ボトルネック」が発生してしまったのです。元CEOのハワード・シュルツ氏が、この混雑した受け取りカウンターを「モッシュピット(もみくちゃの場所)」と表現したほど、その状況は深刻でした。
この「見えない行列」は、パートナー(従業員)たちにも大きな負荷をかけ、かつての人間的な温かみを奪ってしまう。この成功が生んだジレンマこそ、現代のスターバックスが解決すべき、最も重要な課題なのです。
店舗の再発明:「Siren Craft System」という答え
この課題に対し、スターバックスが導き出した答えが、店舗運営を根底から見直す「Siren Craft System」という壮大な改革です。
これは、単なる新しい調理器具の導入ではありません。店舗という「サーバー」の処理能力そのものを向上させるための、ハードとソフト両面からのアプローチです。
例えば、一杯ずつコーヒーを高速で抽出する「Clover Vertica」や、人気のコールドフォームをどこでも作れる携帯機器の導入。これらは、パートナーの無駄な動きを減らし、作業を効率化するための「ハードウェア」の更新です。
そして、繁忙時間帯に「Peak Play Caller」という司令塔役のパートナーを配置し、店内の混雑を解消する。これは、作業の手順(ワークフロー)という「ソフトウェア」の改善です。
さらに興味深いのは、顧客を戦略的に振り分ける、という考え方です。持ち帰りを専門とする「受け取り専用店舗」や「ドライブスルー専用店舗」を増やすことで、取引目的の顧客をそちらに誘導し、従来のカフェ店舗の混雑を緩和する。これにより、「サードプレイス」というブランドの核となる空間を守ろうとしているのです。
環境問題への挑戦:新しい「循環」の仕組み
スターバックスが直面するもう一つの大きな課題が、環境負荷、特に使い捨てカップの問題です。同社は2030年までに廃棄物を50%削減するという野心的な目標を掲げていますが、その達成は容易ではありません。
その解決策の柱となるのが、「リユーザブルカップ(再利用可能カップ)」の普及です。日本では、LINEアプリと連携したカップの貸し出しサービス「Re&Go」が一部店舗で試験導入されています。
これは、これまで「作る→使う→捨てる」という一方通行だったプロセスを、「借りる→使う→返す」という「循環型」の仕組みへと、社会全体で再設計しようとする壮大な試みです。この新しい「ルール」を、いかに多くの人に受け入れてもらえるか。スターバックスの挑戦は続きます。
「サードプレイス」の次へ:未来のコミュニティ

スターバックスの挑戦は、リアルな店舗だけに留まりません。近年、米国で試験的に導入されたのが、NFTを活用した「Starbucks Odyssey」という新しいプログラムです。
これは、顧客を単なる「消費者」から、ブランドを共に創る「コミュニティのメンバー」へと進化させようとする、野心的な実験でした。物理的な店舗(サードプレイス)に加えて、デジタル空間にも新しい形のコミュニティを築こうとしたのです。
この実験は、システムが複雑すぎたことなどから、一度ベータ版を終了しました。しかし、スターバックスが失敗から学ぶ姿は見事です。彼らは「Odyssey」という名前を、今度は人道支援団体への寄付と連動した新しいコーヒー豆のブランド名として再利用しました。複雑な技術の話から、誰もが共感できる社会貢献の物語へと、その意味を見事に転換させたのです。
まとめ
スターバックスの探求を通じて見えてきたのは、常に時代の変化に合わせて自らの「仕組み」を再発明し続ける、驚くべき適応能力でした。
「コミュニティ」と「利便性」という、一見すると矛盾する二つの価値。その両立を目指し、店舗という「サーバー」の処理能力を高め、社会に新しい「循環」の仕組みを提案し、そしてデジタル空間に未来のコミュニ-ティを構想する。
彼らの挑戦は、まだ始まったばかりです。スターバックスの物語は、これからも私たちに多くの「なるほど!」を提供し続けてくれるに違いありません。
【挿絵について】
本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。
さて、全5回にわたるスターバックスの解剖は、これにて一旦の幕引きとなります。この長い探求の旅に、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
『カジのビジネス解体新書』の探求は、まだまだ続きます。また次の「なるほど!」を、一緒に見つけに行きましょう。

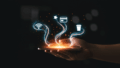
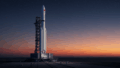
コメント