こんにちは、カジです。
これまでの探求で、私たちはスターバックスの「空間」「商品」「人」という、リアルな店舗体験を支える仕組みを解き明かしてきました。しかし、現代のスターバックスを語る上で、もう一つ欠かせない巨大な柱があります。それは、多くの人のスマートフォンに入っているであろう、あの公式モバイルアプリです。
レジに並ばずとも注文ができ、支払いは一瞬で終わる。ただそれだけでも十分に便利ですが、このアプリの本当のすごさは、単なる利便性の追求だけではありません。その裏側には、私たちの来店を促し、ブランドへの愛着を深め、さらにはスターバックスの経営そのものを支える、極めて巧妙に設計された「デジタルの仕組み」が存在します。
今回は、このアプリと、その中核にある「スターバックス カード」「Starbucks® Rewards」の秘密を解剖していきたいと思います。
すべての始まり:「スターバックス カード」という発明
スターバックスのデジタル戦略の原点は、一枚のプラスチックカードにあります。
「スターバックス カード」が日本でサービスを開始したのは2002年12月。これは、交通系ICカードが国内で初めて導入されたわずか1年後のことで、当時としては非常に先進的な取り組みでした。当初の目的は「小銭を探す手間を省く」というシンプルな利便性の向上でしたが、季節や地域限定のデザインカードが次々と登場することで、いつしか集める楽しみもある「ギフト」としての価値を持つようになりました。
しかし、このカードがもたらした最も大きなインパクトは、全く別のところにありました。私たちがカードやアプリに事前に入金(チャージ)したお金、その「未利用残高」です。
調査によると、2024年3月時点で、全世界の顧客がスターバックスに入金したまま使っていない残高は、約20億ドル(日本円にして約3,000億円)にも達するといいます。米国の銀行の85%が総資産10億ドル未満であることを考えると、これは驚異的な数字です。つまり、スターバックスは顧客から巨額の「無利子ローン」を得ているのと同じ状態なのです。
顧客の利便性のために始まったサービスが、結果として、企業の成長を支える巨大な金融システムへと進化した。この事実は、スターバックスが単なるコーヒーショップではないことを、雄弁に物語っています。
ゲームのように楽しい「Starbucks® Rewards」の仕組み
このカードを基盤として顧客を惹きつけるエンジンが、ポイントプログラム「Starbucks® Rewards」です。これもまた、実に巧みな心理的設計が施されています。
日本のプログラムは、「Green会員」と「Gold会員」という、分かりやすい2階層の仕組みになっています。税込60円の支払いごとに「Star」が1つ貯まり、1年間で250 Starsを集めると、特別な優待を受けられるGold会員に昇格できます。
ここで面白いのは、一般的な「ポイント」ではなく「Star(星)」という言葉を使っている点です。これは、単なる割引のための数字ではなく、集めること自体が楽しくなるような、ゲームのスコアに近い感覚を私たちに与えます。「あと少しでGold Starだ」と感じると、ついもう一杯コーヒーを買ってしまう。そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
この、目標達成の楽しさ(ゲーミフィケーション)を利用した仕組みが、私たちの来店を「義務」から「楽しみ」へと変え、ブランドとの間に特別な関係を築いているのです。
究極の利便性:「モバイルオーダー&ペイ」
そして、このデジタル戦略の集大成とも言えるのが、「モバイルオーダー&ペイ」です。
日本で2019年6月に始まったこのサービスは、カフェで最もストレスを感じる瞬間の一つである「レジの行列」を、完全になくしてくれました。アプリで事前に注文と決済を済ませておけば、あとはお店で商品を受け取るだけ。この究極の利便性は、一度体験すると元には戻れないほどのインパクトがあります。
興味深いのは、このサービスの導入にも日米で戦略の違いが見られる点です。米国では2014年に導入が始まり、わずか9ヶ月で全米展開を完了しました。しかし、そのあまりの人気ぶりに、今度は商品受け取りカウンターに顧客が殺到し、深刻な混雑を引き起こすという新たな問題が発生したのです。
一方、日本での導入は米国から約4年遅れましたが、まずは都心のごく一部の店舗から始めるという、非常に慎重なアプローチを取りました。これは、米国の経験から学び、爆発的な成長よりも、安定した質の高い顧客体験を優先した、賢明な判断だったと言えるでしょう。
「デジタル」と「リアル」の完璧な融合
スターバックスのデジタル戦略のすごさは、単なるIT化ではありません。それは、リアルな店舗体験を、より豊かにするための仕組みとして設計されている点です。
アプリで注文し、店舗でパートナー(従業員)から名前を呼ばれて商品を受け取る。この一連の流れは、デジタルな効率性と、人間的な温かみが融合した、新しい顧客体験です。アプリは、私たちの注文履歴を記憶し、時には好みに合わせたおすすめを提案してくれる、優秀な秘書のような役割も果たします。
このように、デジタル戦略は「サードプレイス」というリアルな体験を破壊するものではなく、むしろそれを補強し、よりパーソナルなものにするためのツールとして、見事に機能しているのです。
まとめ
スターバックスの公式アプリは、単なる決済ツールではありませんでした。
まず「スターバックス カード」で、顧客との間に「無利子ローン」というユニークな金銭的つながりを作り、
次に「リワードプログラム」で、ゲームのような楽しさを提供し、来店を習慣化させ、
そして「モバイルオーダー&ペイ」で、究極の利便性を実現する。
これら三位一体の仕組みが、顧客をスターバックスの「経済圏」に惹きつけ、離れられなくする強力なシステムとなっているのです。
【挿絵について】
本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。
さて、今回はスターバックスの巧みなデジタル戦略の秘密に迫りました。次回はいよいよ最終回。これまでの4回の探求を総括し、スターバックスという巨大なシステムが、この先どこへ向かおうとしているのか、その未来の設計図を考察してみたいと思います。
それでは、また次の探求でお会いしましょう。


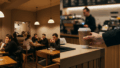
コメント