こんにちは、カジです。
前回の記事では、ゲームボーイが「引き算の哲学」で携帯ゲーム機市場を創造した過程を分析しました。しかし、その王座は盤石ではありませんでした。2004年、ソニーが「21世紀のウォークマン」と銘打った高性能機『PSP(プレイステーション・ポータブル)』を投入し、携帯ゲーム機市場は新たな時代に突入します。
動画も音楽も楽しめる、圧倒的な性能を誇るPSP。対するニンテンドーDSは、お世辞にも高性能とは言えないスペックでした。誰もがPSPの圧勝を予測する中、なぜ最終的に市場を制したのはDSだったのか。全世界での累計販売台数で、DSが約1億5400万台、PSPが約8200万台と、実に2倍近い差がついたのはなぜか。
今回は、この歴史的な競争の裏にあった、両社の根本的な戦略の違いを解剖します。
PSPが提示した「未来」― スペックと多機能
ソニーがPSPで目指したのは、ゲーム、音楽、映像をどこでも楽しめる、まさに「21世紀のウォークマン」でした。当時としては美麗なワイドスクリーン液晶、家庭用ゲーム機に匹敵するパワフルなCPUを搭載し、UMDという独自メディアで高画質な映像コンテンツまで提供する。その戦略は、既存のPlayStationファンや、最新技術に敏感なガジェット好きの心を掴むには十分すぎるほど魅力的でした。
彼らが提示したのは、技術の進化によってよりリッチな体験を携帯するという、いわば「持続的イノベーション」の未来像だったのです。
DSが提示した「答え」― ゲーム人口拡大

一方、任天堂は、PSPと同じ土俵で戦うことを最初から放棄していました。
彼らの目標は、PSPに勝つことではなく、故・岩田聡社長が掲げた「ゲーム人口の拡大」、つまり、これまでゲームを遊ばなかった人々を振り向かせることでした。彼らは、全く別の戦争を、全く別の場所で始めようとしていたのです。
そのための武器が、ゲームの定義そのものを書き換えた、3つの独創的な発明でした。
1. 発明①:『タッチスクリーン』という直感的インターフェース
DSの2画面のうち、下画面に搭載されたタッチスクリーン。これはPDAなどで使われていた「枯れた技術」でしたが、任天堂はこれをゲーム操作の根幹に据えるという「水平思考」で、全く新しい遊びの文法を創造しました。『nintendogs』で子犬を撫でる、『脳を鍛える大人のDSトレーニング』で文字を書く。ボタン操作では不可能な「触れる」という体験が、ゲームとの距離を一気に縮めました。
2. 発明②:『脳トレ』という”非ゲーム”ソフト
DSの成功を決定づけたのが、『脳を鍛える大人のDSトレーニング』の社会現象です。なぜこれが、ゲームに無関心だった中高年層にまで爆発的に普及したのか。それは、このソフトが「ゲーム(娯楽)」ではなく「トレーニング(実益)」という、全く新しい価値を提示したからです。これにより、DSは「子供のおもちゃ」から「家族全員の知的な道具」へと、その姿を変えたのです。
3. 発明③:『すれちがい通信』という社会的繋がり
DSをスリープモードで持ち歩くだけで、見知らぬ誰かとデータ交換ができる「すれちがい通信」。この機能は、ゲームを個人の体験から、現実世界とリンクした社会的体験へと拡張しました。『nintendogs』で自分の子犬が他の飼い主と出会ったり、後の『ドラゴンクエストIX』では「宝の地図」を交換するために人々が街に集まったりと、新しいコミュニケーションの形を生み出したのです。
まとめ
PSPとDSの戦いの結末は、両社が掲げた「問い」の違いによって決まりました。
ソニーが「携帯ゲーム機で、どこまでリッチな体験が可能か?」を問うたのに対し、任天堂は「ゲーム機で、どれだけ多くの人の日常を豊かにできるか?」を問うたのです。
DSの勝利は、後者の問いが、より多くの人々の心を掴んだことの証明でした。彼らはスペックで競うのではなく、ゲームの定義そのものを書き換えることで、全く新しい市場を創造したのです。
【挿絵について】
本記事に掲載されている挿絵画像は、内容の理解を助けるためのイメージです。特定の製品やロゴの正確なデザインを再現したものではありません。
今回は、2画面とタッチ操作で新しい市場を切り開いたDSの戦略を見ました。では次回は、任天堂が初めて本格的な3Dの世界に挑み、その後の業界標準となる「3Dスティック」を生み出した、革命的なハード、『NINTENDO64』の成功と苦悩のメカニズムを解剖してみたいと思います。
それでは、また次の探求でお会いしましょう。

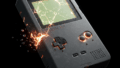

コメント